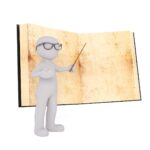
こんにちは。たくまです。
今回は『「叱らない」が子どもを苦しめる』という本をもとに、メンタルを安定させるための子育てについて紹介します。
※実際に学校現場で働いていて、2歳の娘がいる私の考えも含めながら説明しますので、作者の考え方と異なる部分もあると思います。
子どものメンタルを安定させる必要性
学校現場で働いていると、児童が以前よりも幼くなったと感じることが増えました。
「幼い」と言っても、無邪気さや人懐っこさという感じだけでなく、何か自分が上手くいかない時に、我慢ができない児童が多いように感じます。
個人差もあるとは思いますが、子どものメンタルの成長が年齢に追いついていない気がします。
『「叱らない」が子どもを苦しめる』という本では、不登校傾向の児童の増加と、その理由について詳しく説明されていたので、特に私が共感したことを中心に紹介したいと思います。
不登校児童の増加と現代の不登校の理由
『「叱らない」が子どもを苦しめる』では、不登校傾向の児童が増え、その理由も変わってきていることが書かれています。
不登校傾向の児童が増えていることは何となく実感していました。
私もそのような児童と関わる機会がこれまで何度もありました。
対応方法としては、登校刺激はあまり与えず、行けそうな時は来れるように個別に支援していました。
しかし、『「叱らない」が子どもを苦しめる』では、「思い通りにならない場面への強烈な拒否感」が最近の不登校の理由になっていると書かれていました。
そのため、不登校は低年齢化しているともありました。
具体的に「算数の授業がある時は学校に行かない」や「授業時間が長いから登校を渋る」という理由で不登校になる事例が紹介されていました。
実際に現場で働いていて、そのような理由から登校を渋る児童は増えているように感じます。
また、「自分の欲求と環境が与えてくれることの差によって起こる欲求不満に耐える力が不足している」とも書かれていました。
不満や思い通りにならない場面になった時でも、メンタルが安定していれば耐えられると思います。
子どものメンタルを安定させるための親の関わり方
このような背景から、子どものメンタルを安定させていく必要性があると私自身も感じました。
『「叱らない」が子どもを苦しめる』では、親の関わり方が重要ということでした。
具体的に親が子どもとどのように関わっていくことで、メンタルを安定させられるのかを『「叱らない」が子どもを苦しめる』の内容を踏まえながら紹介したいと思います。
子どもの「甘え」に応え、関わり続ける
なぜ、「思い通りにならない場面への強烈な拒否感」が生じるかというと、「ネガティブな自分や未熟な自分を受け入れらない」ことが書かれていました。
小さい頃は、人間として未熟な部分が多いため、親や自分の周りの人々から、様々な指摘を受けます。
そのような周囲からの指摘により、多くの子どもには「子どもが返り」が見られ、甘えが強く出現すると書かれていました。
その時に生じる甘えを、親が受け入れることの蓄積により、「未熟な自分であっても受け入れられる」ことを、子ども自身が実感できるとありました。
ただ、この「甘え」が出てくるのは、子どもがだいたい八歳前後くらいだそうです。
これ以降の年齢になると、指摘された際に「甘え」が生じるのではなく、「離れてしまう」そうです。
そのため、子どもが幼い時に、親や周囲の大人が子どもの未熟な部分を指摘し、その時に生じる子どもからの「甘え」に応え、関わり続けることが重要とのことでした。
そのような関わりを蓄積することで、子どもは「未熟な自分でもあっても受け入れられる」という感覚が積み重なっていくとのことでした。
私も現場の教師として、子どもの不適切な部分は指導し、改善されていれば、認めることを心がけています。
子どもが不適切なことをしたら「押し返す」
先ほど説明した『「甘え」に応え、関わり続ける』ことは親の関わり方で大切なことです。
しかし、そもそも「甘え」が生じるための前段階である、子どもが未熟なために行ってしまう不適切な行為に対して、周囲の大人がきちんと指摘をしなければいけません。
『「叱らない」が子どもを苦しめる』の中では、最近は褒めることに注目して、子どもの不適切な行為から目を背けることで、子ども自身が不快感を経験することが減ってきていることが書かれていました。
そのような不快感を全く経験せず、学校という小さな社会に入ることで、「思い通りにならない場面への強烈な拒否感」が生まれやすくなると感じます。
今までは、何も指摘されなかったのに、学校に入り、教師や友達からの言動によって、不快感を感じ、耐えることができなくなることだと思います。
『「叱らない」が子どもを苦しめる』では、「不適切な行為に対しての指摘」を「世界からの押し返し」という言葉で表しています。
ここでの「世界」は親も含めた自分以外の周囲の人々を指すと思われます。
この「押し返し」は先ほど説明した「甘え」でも必要になる場合があるとのことです。
「親を自分の手足のように扱う発言が見られたり、自分の一部として顎で使って命令してくる」ような場合は、「甘えではない」と書かれていました。
自身の主体性が奪われた感覚に陥るかどうかが「甘え」と「甘えではない」ことの境界線になるそうです。
「甘え」と「押し返し」による効果
「押し返し」により、子どもたちは不適切な行動を指摘され、不快感を抱きます。
その不快感に対して、慰めを求めます。
そこから生じる子どもの「甘え」を親や周りの人々から受容されることで、「未熟な自分であっても受け入れてもらえる」という安心感につながります。
これらの「甘え」と「押し返し」よる効果は、『「叱らない」が子どもを苦しめる』では以下のように紹介されています。
- 自身の未熟性を直視できる
- ネガティブな自分を認められる
- 他責から自責と考える
- 自信をつける
このような効果が見られるそうです。
どれも不登校の予防になり、メンタルを安定せる上でも重要なことだと思います。
最後に『「叱らない」が子どもを苦しめる』の中で、「押し返し」のマナーについて以下のようにまとめられていました。
- 10分を超えて叱らない※それ以上だと子どもには「叱責された」という感覚だけが残り、叱られている内容が入らない
- 人格を否定しない※したことを叱っても、人格を貶すような関わりはもってのほか
- 他の子どもと比べない※子どもの要求に対して「余所は余所、うちはうち」と言いたいのであれば、親が「余所と子ども」を比べてはならない
- 子どもはすぐには変わらないし、親の思い通りにならないと考える※「思い通りにならない」という状況での振る舞いの手本を親が見せる
私もこれらのことに気をつけながら、子育てしたり、学校現場で働いたりしていきたいと思います。







コメント